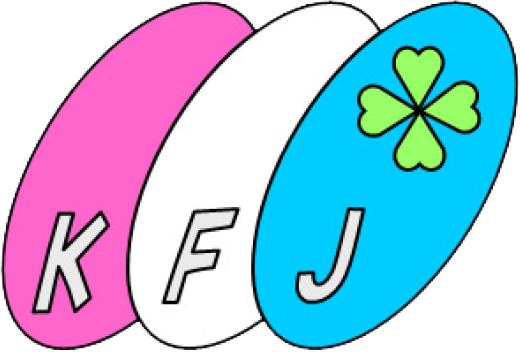職員募集RECRUIT
職員採用試験案内(保育士)
| 【 募集職種 】 |
保育士 0~5歳までの保育業務全般もしくは、療育センターでの療育業務 |
|---|---|
| 【 勤務地 】 |
当法人が運営する保育所(川崎市内)もしくは南部地域療育センター *当初の配属先は可能な限り希望を考慮します。 ・KFJ多摩なのはな保育園(川崎市多摩区登戸2249-1) ・うめのき保育園(川崎市高津区久地3-13-1) ・さくらの木保育園(川崎市中原区下小田中1-11-1) ・まめの木保育園(川崎市中原区小杉町3-1501-A棟3) ・つくし保育園(川崎市幸区戸手本町2-420-1) ・よつば保育園(川崎市川崎区四谷上町14-8) ・南部地域療育センター(川崎市川崎区中島3-3-1) |
| 【 採用日 】 |
令和7年4月1日 *令和6年度内採用も積極的に行います。入職日は、相談に応じます |
| 【 試験日程 】 |
令和6年8月4日(日) 【募集締め切り7月25日(木)必着】 令和6年9月1日(日) 【募集締め切り8月22日(木)必着】 令和6年10月6日(日) 【募集締め切り9月26日(木)必着】 令和6年11月3日(日) 【募集締め切り10月24日(木)必着】 令和6年12月1日(日) 【募集締め切り11月21日(木)必着】 令和7年1月12日(日) 【募集締め切り12月23日(月)必着】 令和7年2月1日(土) 【募集締め切り1月23日(木)必着】 令和7年3月2日(日) 【募集締め切り2月20日(木)必着】 |
| 【 試験内容 】 | 小論文・面接 |
| 【 応募資格 】 | 〇高卒以上で保育士の資格を有する者又は令和6年3月(令和7年度採用は令和7年3月)までに 保育士資格取得見込みの者 |
| 【 提出書類 】 | ①採用試験申込書・自己推薦書(写真添付・署名欄は必ず自署する) *ホームページよりダウンロードして必要事項記入 ②学生の方は成績証明書 既卒の方は該当する資格証の写し |
| 【 申込方法 】 | ①提出書類を下記の住所に郵送してください ②募集締め切り後、受験票をこちらから送付します *提出された書類は、合否に関わらず返却しません |
| 【 応募先 】 | 〒213-0032 川崎市高津区久地3-13-1 社会福祉法人 川崎市社会福祉事業団 事務局 採用担当 044-829-1829 |
給与労働条件(令和5年4月1日現在)
| 【 基本給 】 | ①大学卒 194,100円以上 ②短大・専門卒(2年制) 177,100円以上 ③高校卒 167,500円以上 *職務経験がある方は、一定の基準に基づいて前歴加算されます *昇給年1回(毎年4月) |
||
|---|---|---|---|
| 【 支給例 】 |
(令和5年4月現在) 月給例 251,810円 (大卒初任給・処遇改善手当月割り換算) (上記の給与は基本給・住居手当・不規則勤務手当・処遇改善手当を含みます) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (年収例)賞与・処遇改善は令和4年度実績 大卒 2年目 年収3,859,925円 大卒 5年目 年収4,063,375円 大卒 10年目(主任) 年収4,360,725円 |
||
【 諸手当 】 |
住居手当 その他手当 特別賞与0.5か月(令和5年度末) 年額567,960円(経験年数~5年) 年額646,440円(経験年数5年~10年) 年額780,360円(経験年数10年以上) *処遇改善手当(令和5年度実績)南部地域療育センター配属 年額276,000円~372,000円 |
||
| 【 賞与 】 | 年2回(6月・12月) 年3.65ヶ月(令和5年度実績) | ||
| 【 社会保険等 】 | 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険 退職共済(福祉医療機構・神奈川県福利協会)加入 |
||
【 週休日・休日 】 |
勤務日は、原則週5日 |
||
| 【 休暇 】 |
年次休暇は年間20日付与(翌年度への繰り越し可で最大40日) *4月採用者初年度15日付与(試用期間(6か月)において5日、本採用後10日付与) その他、リフレッシュ休暇5日・結婚休暇・出産休暇・忌引休暇・介護休暇 育児休暇(養育するお子さんが最大3歳まで)・産前産後休暇(産前8週間・産後8週間) |
||
【 定年退職 】
|
定年は60歳で、その後、原則65歳までの再雇用制度があります。
|
Interview先輩職員の声 保育士

成田 朋美うめのき保育園 保育士
入職3年目
- 福祉・保育を目指したきっかけ
- 私自身が通っていたこともあり、保育所は身近な場所でした。小さい子と遊ぶのも、保育所の先生の事も好きだったので、幼いころから自然と保育士を目指していました。進路を決める時、現実的に目指していく中で共働きの両親を思い出し、働くお母さんの助けになりたい、そのためには私の家族を見守り支えてくれた保育園の存在が一番理想だと思いました。家庭のため、社会のために働く母親、父親の支えになればと思ったのがきかっけです。
- 事業団で働いてみての感想
- 外部の研修とは別に、園内でチームごとにテーマを決め、取り組む園内研修があります。園の保育内容や環境を向上させるためにディスカッションや実践しています。先輩後輩関係なく意見を発信できる場で、発信することで意見をもらい自分の考えが整理され実践力がみについていくのが実感できます。
事業団内の保育所合同で子どもの発達に関する内容や、幼児運動についての研修が多く行われていたり、法人内の保育園に行き様子を見学できる交換保育など、実践的な学びと交流の場が多くあります。先輩職員の姿を見て日々学べるのはもちろん、法人内の先輩保育士にも相談でき、非常に心強いです。 - どういう職場にしていきたいか
- 職場には保育者や専門職を含め20数名います。経験年数や職員の年齢はさまざまですが、子どもたちに楽しく過ごしてもらうため、また保護者の方に安心して預けていただけるように日々の保育をしています。どうしたら子どものためになるのか目的や方法で悩むこともありますが、職場の仲間と相談し助け合いながらこれからもよりよい保育をしていけたらと思います。
誰もが安心して生活できる
福祉社会の実現を目指して